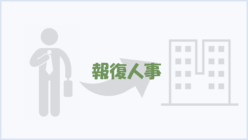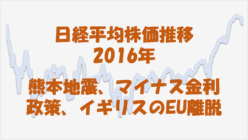 日経平均株価推移
日経平均株価推移 2016年の日経平均株価推移 熊本地震、マイナス金利政策、イギリスのEU離脱
2016年は、米国経済の低成長や原油価格の下落に影響され、緩やかな景気回復基調が続きました。また、実質賃金の減少や長期金利の低水準も見られました。2016年の日本の実質GDPで542.1兆円、成長率は、0.9%でした。
1月4日の大発会、東京株式市場の日経平均は、中国の経済指標悪化から上海株が急落したことを契機に、582円安となり、2008年以来の戦後2番目の下げ幅となりました。
中国メディアの財新と英マークイットが12月の製造業購買担当者景気指数(PMI)は48.2と、11月に比べ0.4ポイント悪化したと発表しました。それにより、1月4日の上海株式市場の上海総合指数は前営業日に比べ6.86%下落しました。サーキットブレーカー制度が発動し、取引時間を1時間半ほど残したまま取引停止となって終わりました。
これにより、投資家のリスク回避姿勢が強まり、世界的な株安となり、日経平均も年初から下落基調が続きました。